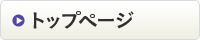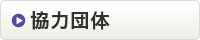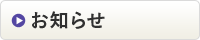現在位置
活動紹介
メルマガ色鉛筆第25号(「こんな夫婦もいる」)
タイトル 「こんな夫婦もいる」ペンネーム うみいろみたい(50代 男性 全盲)
レポートの要旨です。
中途失明した1人の男性。
そんな僕が妻に対して思うことを率直に書いてみた。
妻は楽天家の面があって、あっさりしてると実感することもある。
でも、それが僕にはかえってよかったのかもしれない。
ここから本文です。
彼女とは職場で知り合った。
元気、快活という面が彼女の長所の1つだと思うようになり、そんな彼女をだんだん好きになっていった。
僕には先天的な目の病気があって、夜は極端に見えにくかったので、彼女にとっては付き合い始めた頃からちょっと目が悪い彼氏という感じだったと思う。
でも、普通にデートもしたし、日常生活に特別な支障はなかった。
数年付き合って結婚した。
万人が思い描く仕事、結婚、家庭といった未来予想図を僕も思い描いた。
まさか僕が10年後に失明しているなんて、僕も彼女も想像できなかった。
結婚して8年後、病気が進行してほとんど見えなくなって仕事が続けられなくなった。
僕が仕事をやめることを伝えたら、彼女はあっさり受け入れた。
楽天家の彼女は、生活の不安などもそんなに感じなかったようだった。
彼女自身も働いていたし、幸か不幸か僕達には養わなければいけない子供がいなかったからかもしれない。
ただ、それまで毎日仕事で外出していた僕がずっと家にいるかもしれないということは、気分的な重荷となったようだった。
実際、僕自身にもそれは非常な重荷だった。
夜、彼女が仕事から帰ってきて、自然と職場での出来事などを話し出す。
そんな話に僕は苛立ちを抑えられず、「うるさい」と怒鳴ったことが何度もあった。
見えていた頃の未来予想図は、こうして音をたてて崩れていったのだった。
僕が訓練に行くと言い出した時、彼女はとても喜んだ。
それは、僕の自立を喜ぶというよりも、家の中でゴロゴロしている僕がいなくなることへの喜びだったようだ。
でも結果的に、彼女のそんな姿勢は僕の自立につながっていった。
日本では、人生の途中で見えなくなった主人に寄り添い尽くし続ける伴侶を美しく描きたがるが、彼女にはそんな気はさらさらない。
妻と僕は、僕が見えてた頃と同じように生活している。
お風呂掃除とゴミ出しが僕の役目であることに変わりはないし、買い物もしょっちゅう頼まれる。
洗濯機が壊れて買い替える時、彼女は点字の付いた機種を選んだ。
「私が忙しい時は、自分でできるからいいよね」。
うれしそうに僕に伝えた。
妻のそんな態度がかえって僕の苛立つような力を抜いてくれて、安心できた。
白杖を持った僕と一緒に歩くということにも、妻は最初はだいぶ抵抗を感じたようだった。
それを不謹慎と指摘する人もおられるかもしれないが、彼女のせいではなくて、社会の概念からくるものだと思っている。
何より、本人の僕が白杖を持つことに抵抗を感じたものだ。
特に近所や職場の近くでは、白杖をたたんでリュックサックに片づけて、仲良しの夫婦を演じて手を組んで歩いた。
結局、僕と彼女の距離感は、失明の前も後もそんなに変わっていない。
たまにはケンカもするし、文句も言い合う。
こうして一緒に暮らしながら年を重ねていくのだろう。
それでいいと思っている。
将来、認知症になった彼女を僕が連れて歩かなければならない日がくるかもしれない。
そんなことを想像したことがある。
白い杖を頼りに妻とトコトコと歩くのは、どんな気持ちだろう。
編集後記
失明するというのは、とってもとっても大きな出来事です。
それ故に、とってもとっても劇的、ドラマチックに思えますし、そう思えることにはよい面もあると思います。
ですが、失明するというのは、それだけでは済みませんよね。
それだけになると、そればっかりになると、もう1つの大切なことが見失われるようにも思います。
それはどういうことか?
何が見失われるのか?
ドラマチックなヒーロー、ヒロインではない「うみいろみたい」さんご夫婦に出会ってもらったら、その辺りのことを味わってもらえそう。
そんな思いとともに今回の色鉛筆をお届けしました。
次回の色鉛筆は果たしてドラマチックか、それともドラマチックでないか。
どっちでも楽しみにしてもらえたらうれしいです。
-- このメールの内容は以上です。
発行: 京都府視覚障害者協会
助成協力: 京都オムロン地域協力基金
発行日: 2014年9月19日
☆どうもありがとうございました。
ページの内容は以上です。ここからメインメニューです
所在地と問い合わせ先
郵便番号: 603‐8302
所在地:
京都市北区紫野花ノ坊町11 京都ライトハウス内
公益社団法人 京都府視覚障害者協会
電話(代表):
075-462-2414
ファックス:
075-462-4402
(ファックスは京都ライトハウスと共通です。)
E-Mail:
syomu★nifty.com(メールアドレスは★を半角のアットマークに変更してください)
郵便振替: 01000-5-50226
電話(生活相談):
075-463-8726
電話(ガイドヘルプステーション):
075-463-5569
ファックス(生活相談・ガイドヘルプステーション共通):
075-463-5509
郵便番号: 610-0121
所在地:
京都府城陽市寺田林ノ口11-64 京都府情報コミュニケーションプラザ内
公益社団法人 京都府視覚障害者協会 南部アイセンター
電話:
0774-54-6311
ファックス:
0774-54-6312